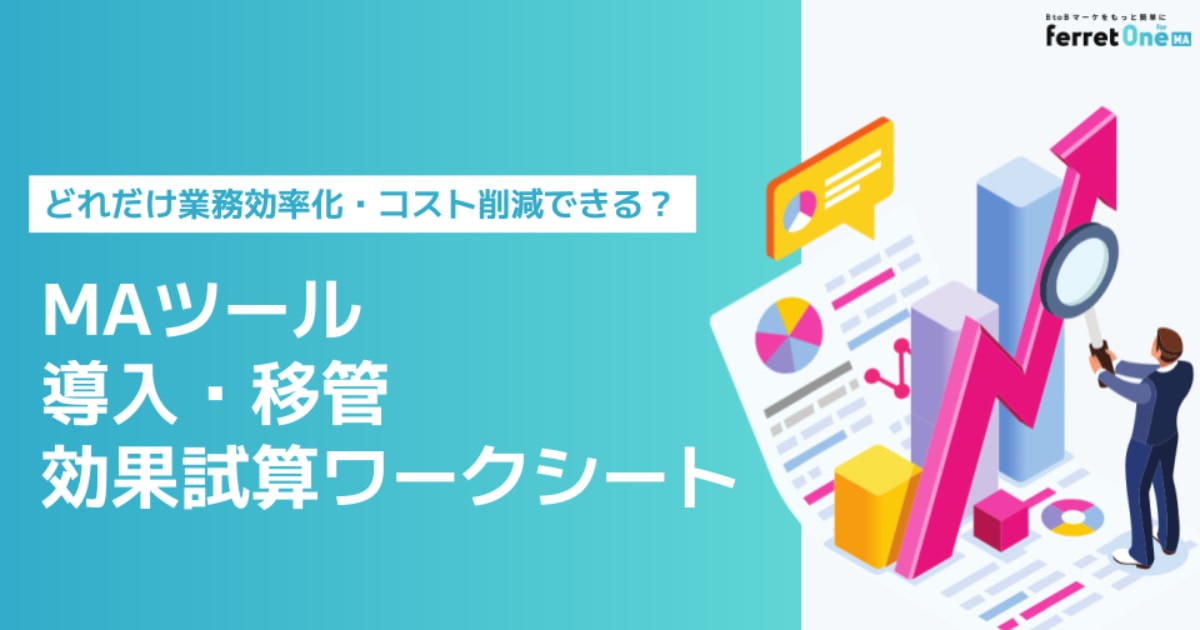セグメント配信とは|一斉配信から脱却するステップと成功事例
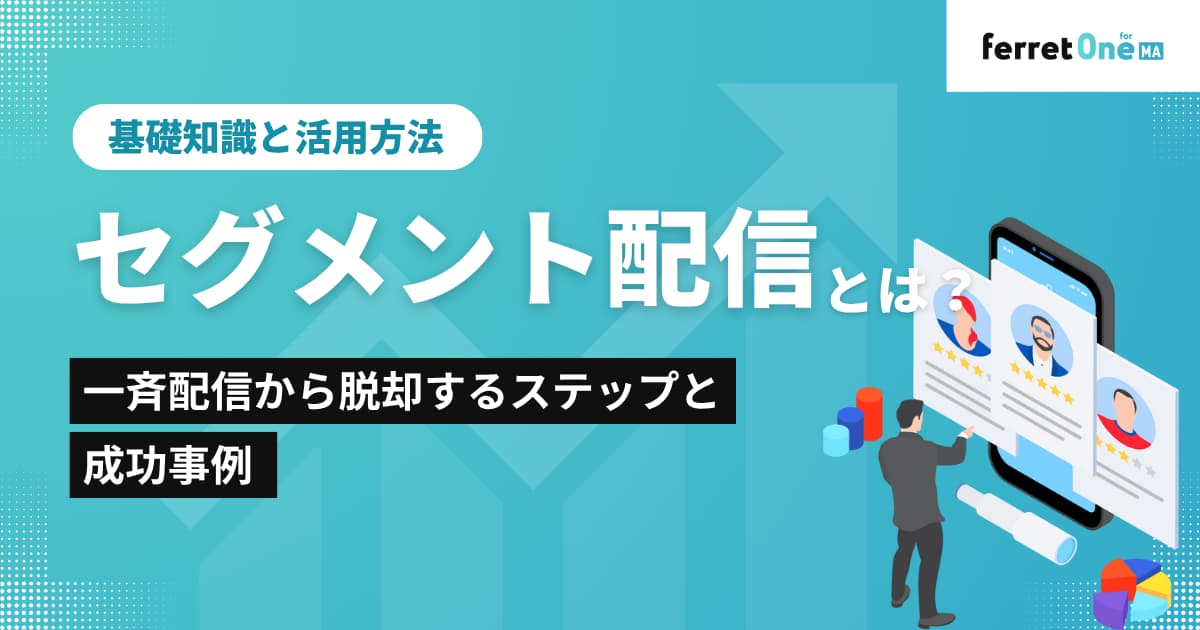

結局、一斉配信しかできていない
メールを送ってもあまり反応がない
MAツールやメール配信ツールを導入したものの、設定が複雑で思ったように使いこなせず、セグメント配信ができないという声は現場でよく聞かれます。
本記事では、セグメント配信の基本知識やメリット・注意点、実践のための具体的ステップ、メール・LINEでの活用方法、さらには「セグメント配信ができない企業の課題と改善策」までをわかりやすく解説します。
セグメント配信とは?
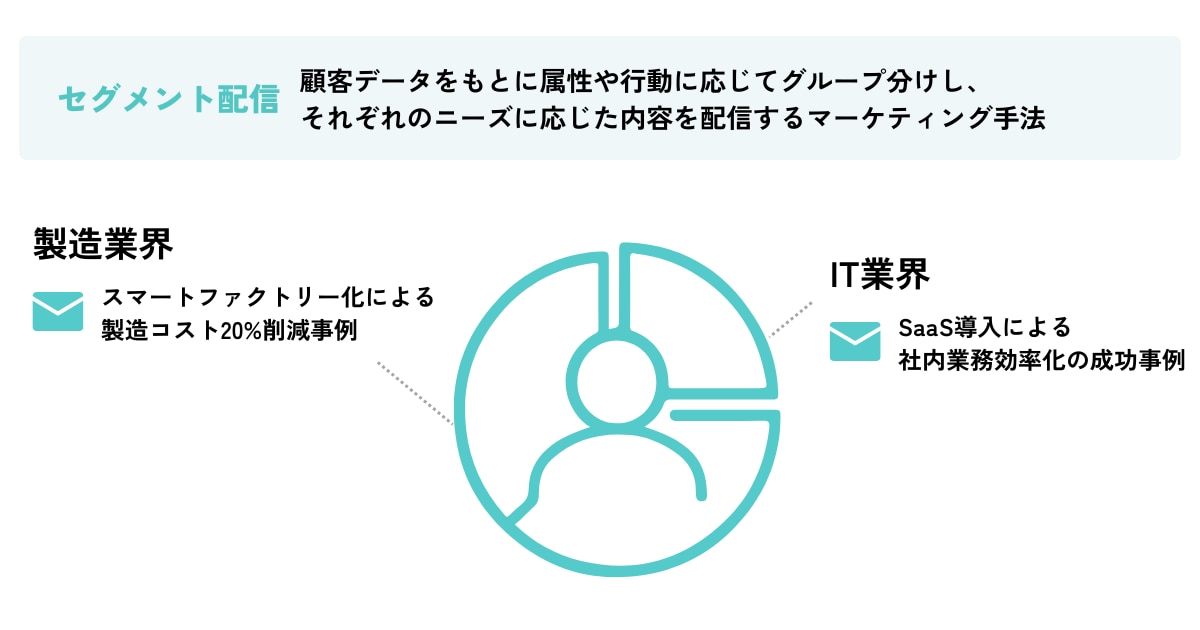
セグメント配信とは、顧客データをもとに属性や行動に応じてグループ分けし、それぞれのニーズに応じた内容を配信するマーケティング手法です。
一律のメッセージを全顧客に送る「一斉配信」とは異なり、顧客にとって関連性の高い情報を届けることで反応率や売上の向上が狙えます。
例えば、以下のようなセグメント配信ができます。
- 過去半年に商談をしたことがある見込み顧客を対象に事例集を送る
- セミナー参加経験のある見込み顧客に次回イベントを案内
- 居住地に合わせた地域限定キャンペーンを配信
見込み顧客のサービスへの検討度に合わせたコンテンツを送ることで顧客体験の向上に直結するのです。
一斉配信との違い
一斉配信は、配信対象者全員に同じ内容のメールを送る配信です。「とにかく多くの人に届けて、どこかで反応があればラッキー」といったアプローチです。一方で、セグメント配信は「関心度が高そうな相手に、確実に響くメッセージを届ける」ことを重視した方法です。
もし「せっかくメールを送っても反応が薄い」と感じているなら、セグメント配信の考え方を取り入れることで、成果の質が大きく変わるかもしれません。
項目 | 一斉配信 | セグメント配信 |
|---|---|---|
ターゲット | 全顧客 | 属性・行動別のグループ |
メッセージ内容 | 一律の内容 | パーソナライズされた内容 |
効果 | 開封率・クリック率が低め | 高い反応・CV率が期待できる |
工数 | 少ない | 設計・管理が必要 |
関連記事:メールマーケティングの始め方5ステップ!初心者でも成果を出すコツと例文
セグメント配信のメリット

セグメント配信を取り入れることで、メールマーケティングの成果は大きく変わります。
ここでは、具体的なメリットを3つの観点からご紹介します。
- 開封率・クリック率・コンバージョン率の向上
- 工数削減・配信効率化
- 顧客ロイヤルティの向上
開封率・クリック率・コンバージョン率の向上
配信リストをセグメントするということは、特定のニーズをもった顧客ごとに分けるということです。
ニーズに合った内容を届けることで、メールを「開きたくなる」「クリックしたくなる」確率が高まります。つまり、最終的なコンバージョン率の向上にもつながるのです。
たとえば、過去に特定の資料をダウンロードしたユーザーに、その続編となるコンテンツを案内することで、「自分に関係のある情報だ」と感じてもらいやすくなります。
工数削減・配信効率化
すべての顧客に同じ内容を送る一斉配信とは異なり、セグメント配信では「必要な人に、必要な情報だけ」を届けることができます。
これにより、無駄な配信回数や工数を減らすことができ、メール配信にかかるチームの負担も抑えられます。
顧客ロイヤルティの向上
「この情報、自分のために送ってくれたのかも」と感じるメール体験は、ブランドに対する信頼感や親しみを生みます。
継続的にそうしたコミュニケーションを重ねることで、顧客との関係性が深まり、ファン化にもつながっていきます。
セグメント配信の注意点と対策
セグメント配信を効果的に行うには、運用時の注意点を理解しておくことが重要です。
ここでは、よくある課題とその解決策をセットで解説します。
- セグメントの細分化による工数の増加
- コンテンツ制作の負担が増える
- シナリオ運用の複雑化
- リードが増やし、データを整備する仕組みが不可欠
セグメントの細分化による工数の増加
セグメントを細かく設定しすぎると、メッセージの作成や配信準備にかかる時間が膨らみ、運用工数が大きくなってしまいます。
対策:
最初から細かい分類はせず、成果に直結しやすい軸に絞る
まずは、運用可能な範囲でセグメントを分けることを意識しましょう。
「業種」「検討フェーズ」などを手掛かりに、反応が大きく変わるポイントに絞ります。成果に直結しやすい要素から始めると、少ない労力でも効果を感じやすくなります。
運用に慣れたり人員が増えたりした段階で、徐々に細分化
「まずはシンプル、徐々に高度化」というステップを意識しましょう。
コンテンツ制作の負担が増える
セグメントごとに異なるコンテンツを用意する場合、制作側のリソースが追いつかず、運用が回らなくなるケースも少なくありません。
対策:
既存コンテンツを活用できるセグメントから取り組む
コンテンツを一から作るのではなく、今あるコンテンツを活用できそうなセグメントから取り組んでいくというのがおすすめです。
コンテンツが足りない場合は、確度の高いセグメントにコンテンツから制作することで、効率的に成果につなげることができます。
メール本文は「共通パーツ+差し替え部分」でテンプレート化
例えば、冒頭の挨拶や導入のみセグメントのニーズに合わせて差し替え、本文は共通化するというように制作プロセスを効率化することで、少ないリソースでも運用していけるようになるはずです。
シナリオ運用の複雑化
セグメント数が増えると、MAツール上のシナリオ設計も複雑になりがちです。管理が煩雑になり、意図しない配信が行われるリスクも高まります。
対策:
シナリオ設計前にカスタマージャーニーとメールの目的を可視化
全体像を見える化することで、不要な分岐や重複を事前に防ぐことができます。
定期的なシナリオの見直し
古い設定や不要な配信を整理する機会を設けておきましょう。
関連記事:MAシナリオとは?その設計、本当に必要?失敗しないための判断基準
リードが増やし、データを整備する仕組みが不可欠
セグメントを作成しても、リスト内のリードが少なければ、コンバージョンの数を確保できず施策効果が出にくくなります。
さらに、セグメント分けに必要な情報(業種・業界・役職など)が不足していると、正確なセグメントが組めません。
対策:
リード獲得施策とデータ整備を同時に進めるようにしましょう。
リードを安定的に増やす仕組みを作る
常に新しいリードを獲得し続けられるよう、複数のチャネルで見込み顧客を獲得する施策を並行して行いましょう。
例えば、展示会・セミナーに定期出展し、名刺情報をMAツールに取り込んだり、サービスサイトでの問い合わせや資料ダウンロードを促す導線を整備します。
セグメント用のデータ項目を明確にする
業種・役職・検討フェーズなど、セグメント分けに必要な情報を定義し、入力漏れをなくす仕組みを整備します。フォーム入力時に、必要なセグメント情報を必須項目として登録したり、手動で登録する項目がある場合は、営業・マーケティング間で「データ入力の役割分担」を明確化しておくといいでしょう。
セグメント配信の実践ステップ

セグメント配信を実際に行う際にどのような手順で実施すればよいのかを解説します。
- セグメントの設計
- パーソナライズされたメッセージ作成
- 配信ツールの活用
- 効果測定と改善サイクル
1.セグメントの設計
セグメント配信する場合のセグメント分けの基準は、ニーズです。同じニーズを持った顧客層に分けていきます。
ただし、「配信するメールを何通りも作成し、そのためのコンテンツも用意する」というのは、膨大な工数となり運用上現実的ではありません。
まずは簡単なセグメント分けで運用していくのがおすすめです。
【代表的かつ成果の出やすいセグメントの分け方】
代表的かつ成果の出やすいセグメントの分け方をご紹介します。
商材別
資料請求やデモ申し込みなどの履歴から見込み顧客の関心がある商材を判断する。
例)商材Aの資料請求をしている→商材Aのニーズがある
- CVの種類別
検討度の高いCVと検討度の低いCVで分けることで、見込み顧客の検討度を判断する。
例)
‐問い合わせ・見積もりを半年以内に行っている→具体的にサービスを探している可能性が高い=検討度が高い
‐ホワイトペーパーをダウンロードした→情報収集の可能性あり=検討度が低い
- 業種・業界別
業種・業界で異なるニーズを持っている場合は、この切り口も有効。フォームで業種・業界を選択式で入力できるようにしておくとセグメント分けに活用可能。
例)
-製造業の顧客→脱アナログの課題感がある
-IT業界の顧客→業務自動化による効率アップの課題感がある
2.パーソナライズされたメッセージ作成
セグメントごとに訴求ポイント(CVポイント)を変え、件名・本文を最適化することで、「自分向けの有益な情報だ」と感じてもらえるメッセージを届けられます。
パーソナライズの精度を高めるための3つのポイントを紹介します。
関連記事:One to Oneメールとは?セグメント配信との違いと効果的な活用法|開封率を高める例文4選付
① 顧客の立場に立つ
まずは、セグメントした顧客層がどんな課題やニーズを持っているのかを具体的に洗い出します。例えば、以下のような観点です。
- どのような立場・役職の人か
- どのような課題を抱えているか
- 予算や決裁権はどの程度あるか
顧客像の理解が浅いままでは、的確なメッセージは作れません。ペルソナ設定を行い、顧客像を明確にしましょう。
ペルソナがない場合は、営業担当へのヒアリングや既存顧客へのインタビュー、口コミサイトの調査などを通して情報を集めることがおすすめです。
②何を送るのか?を明確にする。
見込み顧客が今どの検討段階にいるのかを意識し、そのステップを次に進めるためのコンテンツを届けましょう。
例)
- 認知段階には「業界のトレンドや課題感を整理した記事」
- 比較検討段階には「導入事例や価格感のわかる情報」
- 導入直前には「無料相談・デモの案内」
カスタマージャーニーに沿ったコンテンツ設計を行うことで、スムーズに次の検討ステップへと誘導できます。
③件名・本文を作成する
「あなた宛てのメッセージ」であることを明確に伝える工夫が必要です。
- 置換文字を使う
多くのツールでは、フォームで取得している項目をメールの本文に自動で差し込めるようになっています。名前や業種、会社名などを差し込むことで、より見込み顧客に合わせたメールを作成できます。
- 見込み顧客が使う言葉を用いる
業界特有の言葉や表現、専門用語は相手のリテラシーに合わせて調整しましょう。顧客が普段使っている表現に寄せると共感度を高めることができます。
3.配信ツールの活用
セグメント配信は、MAツール・メール配信ツール・CRM/SFAツールなどを活用することで実現できます。
まずは、自社で導入しているツールでどのようにセグメント配信ができるのかを確認しましょう。
- MAツール
メール配信はもちろん、顧客データの管理、サイト上の行動履歴のトラッキング、スコアリングなど、リードナーチャリングを自動化するためのツールです。
MAツールを使ったセグメント配信の強みは、詳細な顧客情報や行動データをもとにした高度なセグメント分けができることです。そのセグメントを活用し、メルマガやステップメール、シナリオ配信などを戦略的に行えます。
関連記事:MAツールとは?機能・比較・選び方と活用事例を徹底解説
- メール配信ツール
メールの一斉送信やセグメント配信に特化したシンプルなツールです。
メール配信ツールの場合は、顧客属性や登録情報に基づいたセグメント分けとなります。条件分岐が少ない分、容易にできことがメリットです。メール送信以外のナーチャリング施策を実施する予定がない場合は、低コストで導入できるので選択肢の1つとなります。
関連記事:【2025年版】メルマガ配信ツール比較8選| BtoBでの選び方とMAツールとの違い
- CRM・SFAツール
営業活動や既存顧客管理を主目的としたツールです。MAやメール配信ツールと連携し、営業・マーケティング双方の情報を活用できます。
リード獲得後の商談履歴や取引情報をもとに、セグメント分けができます。より受注に近い顧客に絞ったターゲティングやナーチャリング施策を実現可能となります。
関連記事:CRMとは?SFA/MAとの違い、機能、選び方、導入手順まで徹底解説
関連記事:SFAとは?CRM・MAとの違いと失敗を防ぐ選定基準
4.効果測定と改善サイクル
セグメント配信を行ったら、効果測定と改善を繰り返して効果を最大化していきましょう。
分析指標の設定から改善フローまでを明確にしておくと、施策の質を継続的に高められます。
ここでは効果測定・分析で見るべき指標や観点をご紹介します。自社で振り返りをする際の参考にしてみてください。
効果測定で見るべき主な指標
開封率
件名や配信タイミングの適切さを測る指標。低い場合は件名の改善や送信時間の見直しを検討しましょう。
クリック率(CTR)
メール内リンクやコンテンツの魅力を測定。クリックされない場合はコンテンツの見直しやリンク配置の改善が必要です。
コンバージョン率(CVR)
資料請求や問い合わせなど、最終的な成果を示す指標。セグメントの精度やCVポイントを見直す目安となります。
配信停止率(オプトアウト)
ユーザーの離脱を防ぐための重要指標。配信頻度や内容が適切かを判断する材料となります。
分析の観点
セグメント
どのセグメントの反応が高いかを把握し、分け方や精度を改善していきます。
コンテンツ
記事・事例・セミナーなど、どのコンテンツが刺さったかを把握します。
配信タイミング
配信時間や曜日ごとの反応率を見て、最適な送信スケジュールを検証します。
改善サイクルの進め方
MAツールやメール配信ツールのレポートを定期チェックするようにしましょう。PDCAは小さく回すことが重要です。細かい改善を繰り返すことで、施策精度が着実に向上します。
- KPI設定:開封率・クリック率・CV率など、目標を定量化します。
- 仮説立て:指標低下の原因を推測し、改善仮説を立てる。
- 施策実行:メール内容・セグメント条件・配信タイミングなどを調整します。
- 結果分析・ナレッジ化:成果から仮説が検証できたかを確認しましょう。再現性のある施策として社内に共有することも重要です。
- 次施策へ展開:改善サイクルを継続し、施策全体をブラッシュアップしていきましょう。
MAツールを使いこなせず一斉配信になってしまう課題と解決策
セグメント配信を実現したいのに、ツール運用や社内体制の問題で「結局一斉配信しかできない」というケースは少なくありません。
ここでは、よくある課題とその具体的な解決策をセットで紹介します。
- 課題1:ツールのカスタマイズや設定が複雑すぎて使いこなせない
- 課題2:顧客データが整理されず、セグメントが作れない
- 課題3:運用が属人化し、設定やフローが不明瞭
簡単チェックリスト
- MAツールの初期設定が複雑すぎる→はい①
- セグメント設計が細かすぎて手が回らない→はい①
- 配信作業の締切に追われ、検証時間がない→はい①
- 顧客データが整理されていない→はい②
- データ登録のルールがない→はい②
- 「一斉配信が当たり前」になっている→はい②
- マニュアルやトレーニング資料が共有されていない→はい③
- 専任担当者がいない・属人化している→はい③
課題①~③に該当する項目です。「はい」があった場合、各課題の詳細を確認してみてください。
MAツールの活用がネックとなって、セグメント配信できていない可能性があります。
課題①:MAツールのカスタマイズや設定が複雑すぎて使いこなせない
MAツールを導入する際に機能を詰め込みすぎたり、カスタマイズしすぎたりした結果、運用担当が変わるたびにブラックボックス化してしまうケースは珍しくありません。
「タグやシナリオが複雑すぎて手が出せない」「誰が設定したのかわからない」といった声も多く聞かれます。
解決策:使いやすいMAツールへの乗り換えや再設計を検討
思い切ってMAツールを見直す
社内で活用できる人材がいない場合は、使いやすいMAツールへの乗り換えがおすすめです。
高機能なMAツールはコストが高く、基本機能しか使えていないのなら投資対効果が下がります。最近は初心者向けで直感的に使えるツールも多く、使う機能に絞ることでコスト削減にもつながります。
関連記事:MAツールの乗り換えはいつ・どう進める?費用対効果で選ぶ比較ポイントと失敗しない手順
既存ツールを活かすなら外部支援を活用
現在のMAツールをどうしても活用したい場合は、ベンダーやコンサルティング会社の支援を受け、設計の見直しや運用フローを整理するとよいでしょう。
課題②:顧客データが整理されず、セグメントが作れない
顧客情報が複数のシステムに分散していたり、登録ルールが社内で統一されていなかったりすると、情報がバラバラになりがちです。
さらに、属性情報が更新されず放置されるケースも多く、結果的に精度の高いセグメントを作成できず「結局一斉配信しかできない」という状況に陥ります。
解決策:データの一元管理から始める
- ツール連携で分散した顧客情報を統合
セグメント配信の第一歩は、データ基盤の整備です。
最近では、複数のツール間でスムーズに連携できる仕組みが充実してきています。まずは、自社で使っているMA・SFA・CRMが連携可能かを確認してみると良いでしょう。
たとえば、当社のMAツール「ferret One for MA」は、SFAツール「Salesforce」との双方向連携が可能です。これにより、営業活動で得た情報をリアルタイムにMAへ反映し、常に最新の状態でセグメントが組めるようになります。
分散した顧客情報をMA・SFA・CRMに統合し、「どのツールで見ても常に正しい情報にアクセスできる」状態を目指しましょう。
- 顧客データの登録ルールを周知
①入力するデータを決める
顧客データを正しく活用するためには、社内全体で共通の登録ルールを持ち、それを継続して運用する仕組みが欠かせません。
まずはマーケティング・営業活動をするために欠かせない基本情報から整理しましょう。
‐名前(会社名・担当者名)
‐メールアドレス
‐業種
‐役職
‐現在の検討フェーズ(例:情報収集中/比較検討中/導入直前 など)
これらの情報をベースに、後から必要に応じてBANTなどの詳細情報を追加していくと、運用がスムーズになります。
②情報更新のフローと担当者を明確にする
ルールを決めた後は、それを継続的に守るための仕組みづくりも重要です。
-誰がどのタイミングで情報を更新するのか
-更新漏れをどう防ぐのか
-入力ミスや形式ゆれをどう防止するのか
といった観点で、更新フローを文書化しておくと、チーム内での認識ずれが起きにくくなります。
たとえば、「営業が商談終了後に必ず検討フェーズを入力する」「マーケが月1回データをレビューする」といったルールを設定しておくとよいでしょう。
課題③:運用が属人化し、設定やフローが不明瞭
担当者の交代や情報共有不足により、MAツールや配信設定のノウハウが属人化してしまうケースは少なくありません。
「誰が設定したかわからないシナリオが残っている」「運用マニュアルが存在しない」という状況では、新任者が運用を引き継げず、改善が進まないばかりか、運用が止まってしまう原因になります。
解決策:社内外のサポート体制を整備する
- ベンダーの各種サポートを積極活用
ベンダー(ツール提供企業)が用意しているオンボーディングプログラムや伴走支援を活用しましょう。操作や設定の基本を習得できるほか、マーケティングのノウハウまで学ぶことができます。
運用フロー・マニュアルの簡易化と共有
権限設定や配信ルール、命名規則などの基本情報もまとめておくと管理がしやすくなります。
外部コンサル・マーケティング支援の導入
ツールの設計や施策の設計で手詰まりになった場合は、外部のプロに依頼するのも有効です。「施策ごとに成果を可視化したい」「企業属性ごとにナーチャリングを自動化したい」などの課題に応じた提案を行うサービスも増えています。
セグメント配信で成果を出すための運用のコツ
セグメント配信の効果を持続的に高めていくには、日々の運用の中で意識すべきポイントがあります。
ここでは、実務で特に大切にしたい3つのコツをご紹介します。
- 「顧客目線」を忘れない
- 効果検証を繰り返して、精度を高める
- 最初はシンプルに、小さく始める
「顧客目線」を忘れない
毎日の業務に追われていると、つい「とりあえず送ること」が目的になってしまいがちです。
しかし、セグメント配信の本来の目的は、「顧客の心を動かし、行動を促す」ことにあります。配信前には、次のような問いを自分に問いかけてみましょう。
- この情報は、相手にとって本当に役立つだろうか?
- 相手の検討フェーズに合った内容になっているか?
- 今、このタイミングで送る意味があるか?
こうした「顧客目線」を習慣にすることで、自然とメッセージの質も成果も向上していきます。
効果検証を繰り返して、精度を高める
送る前はどんなに良さそうに思えた施策でも、やってみると想定外の結果になることも少なくありません。
たとえば、
- 開封率は高いがクリックされない → タイトルは良いが内容が弱いかもしれない
- 特定セグメントだけCV率が高い → その属性が成功要因かもしれない
このように、結果をもとに仮説を見直し、再現性を高めていくことで、セグメント配信の効果は確実に積み上がっていきます。
段階的に高度な施策へ
最初から複雑なセグメントを目指さなくてもかまいません。社内のリソースを加味して、実現可能な範囲で最大限の成果を出すようにしましょう。
運用を続けていくことで、効率化できる業務が見つかり、スキルアップによってより高度なセグメントにも挑戦できるようになるはずです。
最初はシンプルに、小さく始める
「セグメント配信=複雑なシナリオや大量のコンテンツが必要」というイメージがあるかもしれませんが、最初から完璧を目指す必要はありません。
むしろ、まずは限られたセグメントや少ないパターンでスタートし、確実に成果が出る型を見つけることが大切です。
たとえば、
- 「資料請求者」と「イベント参加者」でメール内容を分けてみる
- 同じメールでも、導入文だけを変更してテストしてみる
このような小さな工夫を積み重ねていくうちに、運用にも慣れ、リソースに余裕が出てきたタイミングで、より高度なセグメント施策に挑戦できるようになります。
セグメント配信のセグメント分け事例
当社が運営する「ferretメディア」のメルマガではどのようなセグメント分けでメルマガを配信しているのかをご紹介します。
「ferretメディア」では、会員の多様な属性や関心を踏まえ、一律の情報配信ではなく個別最適化を重視し、メルマガのセグメント配信を行っています。
①職種によるセグメント
まず、会員登録時の回答を基に「職種」で「ターゲット」と「非ターゲット」に大きく分類します。
- ターゲット職種:カスタマーサクセス、経営企画、営業・販売、制作・編集、マーケティング
- 非ターゲット職種:開発デザイン、その他・コーポレート、学生・主婦、職種未選択
②興味関心による詳細なセグメント化
さらに、登録時に選択された「興味のある分野」に応じて、配信セグメントを10パターンに細分化しています。
- 制作・デザイン(ターゲット/非ターゲット)
- コンテンツマーケティング(ターゲット/非ターゲット)
- 広告(ターゲット/非ターゲット)
- ビジネス戦略・マネジメント(ターゲット/非ターゲット)
- ナーチャリング・営業商談
- 関心不明層(不可層)
これにより、関心に沿ったメルマガのみを届ける仕組みを構築しています。
▶ なぜ非ターゲットにもメルマガを送っているのか?
理想はターゲット職種への配信のみでCV数を十分に確保することです。
ただ現状では興味関心を未選択のまま登録している会員も一定数存在することもあり、ターゲット職種だけの配信ではCV数の担保が難しく、非ターゲット層への配信も継続して行っています。
【配信結果】セグメントあり・なしの成果の違いを公開
本当にセグメント配信は効果があるのか?実際にメールを送付した結果を見てみましょう。
セグメント配信事例① 一斉配信とセグメント配信の違い
一斉送信と広告セグメントへの配信結果を比較しました。
実際に、セグメント配信の方が開封率、クリック率ともに向上していることが分かります。
ケース① 送ったメルマガのCVポイント:リスティング広告関連のWP
一斉送信 | セグメント配信 | |
開封率 | 6.02% | 22.90% |
クリック率 | 1.17% | 4.98% |
ケース② 送ったメルマガのCVポイント:データ戦略の成功事例WP
一斉送信 | セグメント配信 | |
開封率 | 5.64% | 20.13% |
クリック率 | 1.03% | 3.25% |
セグメント配信事例② セグメント配信の粒度を変えた事例
さらに、セグメントの中でもより小さなセグメントに切り分けて配信した事例もご紹介します。
「コンテンツマーケティング」セグメント全体への配信結果と「コンテンツマーケティング」の「ターゲット」に絞ったセグメントへの配信結果を比較しました。
こちらの場合でも、セグメントの粒度を細かくした方が、開封率、クリック率ともに向上していることが分かります。
ケース① 送ったメルマガのCVポイント:メールマーケ関連のWP
「コンテンツマーケティング」セグメント | さらにターゲットに絞ったセグメント | |
開封率 | 15.18% | 21.40% |
クリック率 | 0.93% | 3.60% |
ケース② 送ったメルマガのCVポイント:動画制作関連のWP
「コンテンツマーケティング」セグメント | さらにターゲットに絞ったセグメント | |
開封率 | 11.91% | 26.58% |
クリック率 | 0.48% | 1.40% |
セグメント配信の実施・改善事例

当社ferretで、実際にセグメント配信を行った結果と、そこからどのように次回の配信への改善策を見つけたかをご紹介します。
- セグメント配信を始めたきっかけ:バーティカル戦略によるセミナー施策の強化
- セグメント配信の結果:クリック率・CV率は高いが、成果数は減少
- セグメント配信結果の分析:セグメント母数不足が根本原因と分かる
- 改善策:データクレンジングとリスト整備を実施
セグメント配信を始めたきっかけ:バーティカル戦略によるセミナー施策の強化
特定業界に焦点を当てたバーティカル戦略の一環として、製造業向けのセミナーを開催。
セミナー集客のために、製造業セグメント向けたメルマガ配信を実施し、対象業界の関心を高める取り組みを進めていました。
その結果、メルマガ配信全体の中でセグメント配信が占める割合が増加していきました。
セグメント配信の結果:クリック率・CV率は高いが、成果数は減少
セグメント配信はターゲットが絞られているため、クリック率やコンバージョン率は高く、一定の効果は確認できました。
しかし、セグメント母数の少なさが原因で、全体のCV(セミナー申し込み数)は減少。ferretのセミナー申し込みの8割を担うメルマガ経由の成果が減少し、結果として商談数の減少にもつながるリスクが浮き彫りになりました。
セグメント配信結果の分析:セグメント母数不足が根本原因
さらに分析を進めたところ、新規リストには「業種データ」が未登録のケースが多く、セグメント化対象となるリストの母数がそもそも少ないという課題が判明。
セグメント配信を増やす戦略自体は効果的でも、データ整備が追いついていない状態では成果を最大化することが難しいという構造的な問題が見えてきました。
改善策:データクレンジングとリスト整備の重要性
セグメント配信を成功させるには「配信対象リストの母数確保」が不可欠であると再認識。データクレンジングを実施し、業種データの整備や新規リストの属性情報充実を進めることで、より精度の高いターゲティングとセミナー集客の最大化が可能になるという改善方針を得ました。
3ヶ月の平均率 | 到達率 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | CV数 | CV率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/10〜12月セグメントのみ | 99.77% | 16.84% | 14.08 | 2.95% | 6.55 | 1.38% |
24/1〜3月セグメントのみ | 99.95% | 18.18% | 12.88 | 2.45% | 5.86 | 1.11% |
23/10〜12月セグメント以外 | 99.94% | 19.27% | 54.73 | 0.54% | 17.27 | 0.17% |
24/1〜3月セグメント以外 | 99.07% | 20.24% | 61.83 | 0.57% | 12.12 | 0.15% |
まとめ
セグメント配信は、顧客ごとに最適なメッセージを届けることで、開封率やコンバージョン率を高められる効果的なマーケティング施策です。
しかし、ツールの設定やデータ管理が複雑になりやすく、導入しても一斉配信に戻ってしまう企業も少なくありません。
重要なのは、いきなり完璧を目指さず、小さな成功体験から始めること。今あるデータでできる簡単なセグメントからスタートし、段階的に改善を繰り返すことで、無理なく効率的な配信体制を構築できます。
この記事を参考に、自社の配信施策を見直し、顧客一人ひとりに寄り添ったマーケティングを進めていきましょう。
もしも、「ツールが複雑で一斉配信から抜け出せない」「もっと使いやすいツールで効率的に成果を出したい」と感じている方は、当社の「ferret One for MA」もご検討ください。